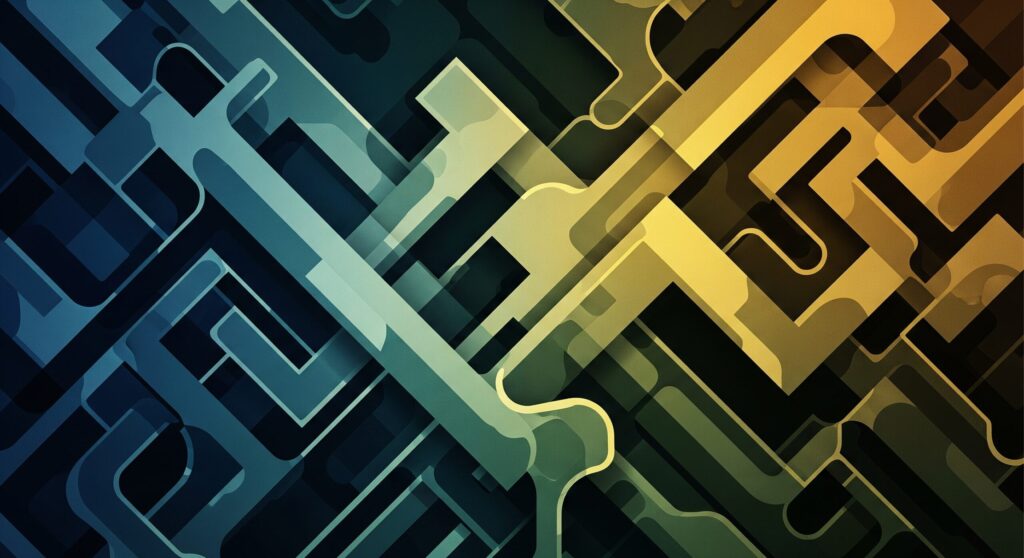「親から会社を継ぐことになったけど、自社株の評価額が思ったよりも高くて…」
「相続税を払いきれないかもしれない。このままでは会社が危ない…」
中小企業の経営者の方や、これから会社を相続することになった方にとって、自社株(非上場株式)の相続税は、会社の未来を左右する非常に大きな問題です。上場株式と異なり、自社株は市場で売買できないため、換金性が低く、多額の相続税が発生しても「納税資金がない」という事態に陥りやすいのが現実です。
納税ができない場合、最悪のシナリオは、会社を売却したり、事業用資産を手放したりして納税資金を捻出することになり、結果的に事業の継続が困難になることです。しかし、諦める必要はありません。自社株の相続税が払えない状況に直面したとしても、利用できるいくつかの対策や制度が存在します。
本記事では、M&Aや事業承継を考える経営者や、自社株の相続税の支払いに不安を感じている方に向けて、自社株の相続税が払えない場合の具体的な対策や、利用できる制度、そして専門家への相談の重要性を、どこよりも分かりやすく徹底解説します。大切な会社と事業を守り、円滑な事業承継を実現するための知識を、ぜひインプットしてください。
1. なぜ「自社株の相続税が払えない」という事態が起こるのか?
自社株の相続税が払えない事態は、主に以下の要因が絡み合って発生します。
1-1. 自社株の「評価額」と「換金性」のギャップ
- 高い評価額: 会社の業績が好調であったり、多くの不動産や含み益のある資産を保有していたりすると、税務上の自社株評価額は高くなります。しかし、これはあくまで税務上の評価であり、すぐに現金化できる価値ではありません。
- 低い換金性: 上場株式のように市場で自由に売買できるわけではないため、売ろうと思ってもすぐに買い手が見つからず、現金化が困難です。
1-2. 相続財産における「自社株の比率の高さ」
多くの中小企業では、経営者の資産の大部分が自社株で占められているケースが少なくありません。現預金や他の相続財産が少ない場合、高額な自社株評価額に対する相続税の納税資金を確保できなくなります。
1-3. 相続税の「納税期限」の短さ
相続税の申告と納税の期限は、原則として相続開始の翌日から10ヶ月以内と定められています。この短い期間で、複雑な自社株の評価や遺産分割協議、そして納税資金の確保まで行うのは、非常に大きな負担となります。
1-4. 生前の相続税対策の不足
生前から計画的な相続税対策(自社株の評価引き下げ策や、納税資金の準備など)を行っていなかった場合、相続発生後に高額な税金に直面することになります。
2. 自社株の相続税が払えない場合の「具体的な対策」
自社株の相続税が払えない場合でも、いくつかの対策を講じることが可能です。
対策1:事業承継税制(納税猶予・免除)の活用
自社株の相続税対策として最も強力な制度であり、最優先で検討すべきです。
- 制度の概要:非上場会社の自社株式を後継者が相続(または生前贈与)で取得した場合に、その株式にかかる相続税(贈与税)の納税を100%猶予し、最終的に免除する制度です。
- メリット: 後継者は多額の税金を納税することなく、会社の経営に集中できます。
- デメリット・注意点: 適用を受けるための要件が複雑であり、承継後も事業継続や雇用維持などの「継続要件」を満たし、定期的な報告義務を果たす必要があります。要件を破ると猶予が取り消され、多額の税金と利子税を一括で支払うことになります。
- 相続発生後でも適用可能:原則として「特例承継計画」の提出が必要ですが、相続発生前に提出していなかった場合でも、相続発生の翌日から10ヶ月以内(相続税申告期限まで)に手続きを完了させれば適用できる特例があります。ただし、非常にタイトなスケジュールとなるため、迅速な対応と専門家のサポートが不可欠です。
対策2:延納(分割払い)制度の活用
相続税を一括で納税することが困難な場合、延納という分割払い制度を利用できます。
- 制度の概要:相続税の納税額が10万円を超える場合で、金銭で一括納付が難しいと認められる場合に、担保を提供することで、税金を最長20年間で分割払いできる制度です。
- メリット: 現金をすぐに用意できない場合でも、納税期限を延長できる。
- デメリット・注意点:
- 利子税が発生: 延納期間中、毎年利子税がかかります。これは、税金に対する利息のようなものです。
- 担保の提供: 延納税額に見合う担保(不動産、有価証券、納税保証書など)を提供する必要があります。自社株を担保にできる場合もありますが、税務署の審査が必要です。
- 延納計画の策定: 税務署へ延納申請書を提出し、承認を得る必要があります。この計画が適切でないと承認されない場合があります。
対策3:物納(現物納付)制度の活用
延納でも納税が難しい最終手段として、物納という現物での納付制度があります。
- 制度の概要:延納によっても金銭での納税が困難な場合に、特定の相続財産(不動産、株式、債券など)を国に引き渡すことで、相続税を納付できる制度です。自社株も物納の対象となる場合があります。
- メリット: 現金が全くない場合でも、納税義務を果たせる。
- デメリット・注意点:
- 最終手段: 延納でも納税が難しい場合に限られます。
- 厳しい要件: 物納の対象となる財産は厳しく限定され、物納できる自社株は「譲渡制限がない」「換金性が高い」など、非常に厳しい要件があります。多くの中小企業の自社株は、この要件を満たすのが難しいのが現実です。
- 会社の支配権への影響: 自社株を物納する場合、その株式は国のものとなり、会社の支配権に影響を与える可能性があります。
- 手続きの煩雑さ: 物納の申請には多大な書類と審査が必要で、非常に時間がかかります。
対策4:会社の資産売却や借入による納税資金の捻出(要注意)
上記の制度活用が難しい場合、会社や後継者が納税資金を捻出する方法を検討することになりますが、これにはリスクが伴います。
- 会社による借入: 会社が金融機関から借り入れて、その資金で後継者に役員報酬を支払う、あるいは配当を出すことで、後継者が納税資金を確保する方法です。
- 注意点: 会社の財務状況を悪化させるリスクや、会社の借入が後継者の個人保証につながるリスクがあります。また、配当や役員報酬は所得税・住民税の対象となります。
- 事業用資産の一部売却: 会社が所有する不動産や遊休資産の一部を売却して資金を捻出し、それを後継者に渡す方法です。
- 注意点: 会社の事業に影響が出ないか、売却益への法人税や消費税を考慮する必要があります。
- 自社株の一部売却(M&Aなど): 後継者が取得した自社株の一部を、外部の第三者(別の企業など)に売却して納税資金を確保する方法です。
- 注意点: 買い手を見つけるのが困難な場合がある。事業承継税制を利用している場合、納税猶予が取り消されるリスクが非常に高い(売却した部分について)。
5. 相続税の負担を軽減するための「生前対策」の重要性
「自社株の相続税が払えない」という事態を避けるためには、やはり生前の対策が最も重要です。
5-1. 自社株の評価額対策(株価対策)
相続発生前に、自社株の評価額そのものを引き下げておくことで、将来的な相続税・贈与税の負担を軽減できます。
- 役員退職金の支給: 経営者への退職金を支給することで、会社の利益を圧縮し、株価評価の基準となる利益や純資産を減らすことができます。退職金は税制優遇があるため、効果的な対策です。
- 配当の実施: 会社の内部留保を配当として株主に還元することで、株価を引き下げる効果が期待できます。
- 不要資産の売却: 事業に直接関係のない遊休資産や含み益の大きい不動産などを売却し、会社の資産をスリム化することで、純資産価額方式による株価を下げられる場合があります。
5-2. 納税資金の計画的な準備
- 生命保険の活用: 生命保険の死亡保険金は、一定額まで相続税の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)があります。この非課税枠を活用することで、納税資金を確保しつつ、相続税を軽減できる場合があります。
- 現金・預貯金の確保: 相続発生後すぐに納税できるよう、相続財産に占める現預金の割合を高めておくことも重要ですし、後継者自身も個人で貯蓄しておくことが望ましいです。
5-3. 遺言書の作成と遺産分割の円滑化
- 遺言書: 遺言書で後継者に自社株を集中して相続させる旨を明確にしておくことで、遺産分割協議をスムーズにし、納税を担う後継者を明確にできます。
- 他の相続人への配慮: 自社株を後継者に集中させる場合、他の相続人への配慮として、他の財産を多めに相続させたり、代償金を支払う準備をしたりすることも重要です。
6. まとめ:「払えない」状況に陥る前に、まずは専門家へ
自社株の相続税が「払えない」という状況は、多くの中小企業で起こりうる現実的な問題です。しかし、事業承継税制の活用、延納、物納といった制度や、様々な生前対策を組み合わせることで、この困難を乗り越える道は必ず見つかります。
- 納税猶予・免除: 事業承継税制(特例措置)が最も強力な解決策。相続後でも適用可能。
- 分割払い: 延納制度で最長20年間の分割払いが可能だが、利子税と担保が必要。
- 現物納付: 物納制度は最終手段だが、自社株は要件が厳しい。
- 納税資金の捻出: 会社の借入や資産売却も手段だが、会社の財務への影響に注意。
- 最善策は「生前対策」: 株価対策、納税資金準備、遺言書作成などで、そもそも「払えない」状況を防ぐ。
何よりも重要なのは、「相続が発生する前」、あるいは**「払えないかもしれない」と不安を感じたその瞬間**に、税理士をはじめとするM&A・事業承継の専門家に相談することです。専門家は、あなたの会社の状況を正確に把握し、法的に有効かつ最も効果的な対策を提案してくれます。
早めにプロのサポートを得ることで、予期せぬ税負担に慌てることなく、あなたの大切な会社を、安心して次の世代へとバトンタッチできるでしょう。