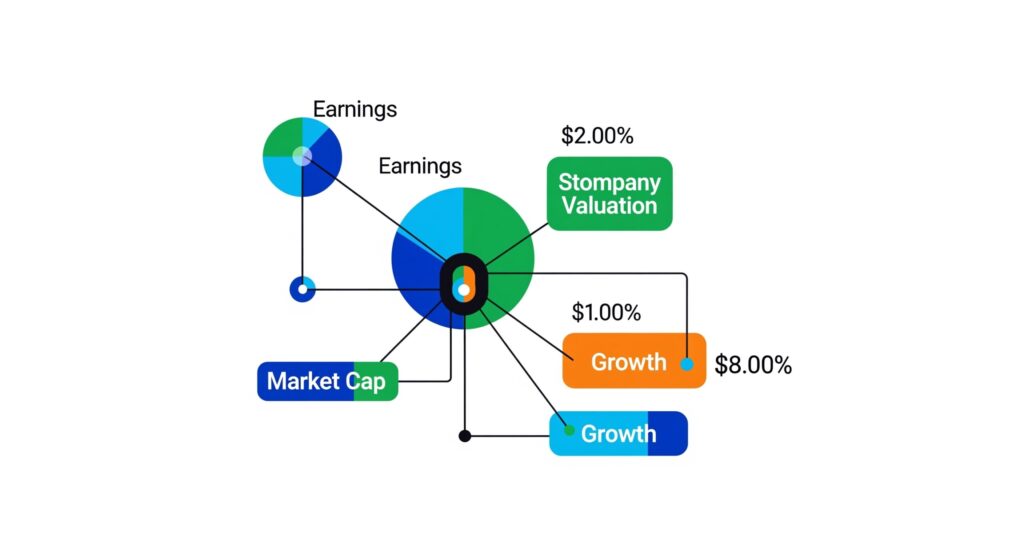「会社の株式の価値って、どうやって計算するんだろう?」
「M&Aや事業承継を検討しているけど、ざっくりとでも自社株の評価額を知りたい」
中小企業の経営者にとって、自身の会社が発行している**「自社株(非上場株式)」の価値**は、M&Aや事業承継を進める上で非常に重要な情報です。会社を売却するならいくらになるのか、親族や社員に譲るなら相続税や贈与税がいくらかかるのか。これらを判断するためには、自社株の評価額を知ることが不可欠です。
しかし、税務署に提出するような正式な自社株評価は、専門的な知識が必要で複雑なため、税理士に依頼するのが一般的です。それでは、「もっと手軽に、ざっくりとでも自社株の価値を知る方法はないのだろうか?」と思う方もいるでしょう。
ご安心ください。本記事では、M&Aや事業承継を考える経営者の方に向けて、**誰でもできる自社株評価の「簡易計算方法」**を、どこよりも分かりやすく徹底解説します。正確な税務申告には使えませんが、自社の状況を把握し、今後の事業承継やM&A戦略を検討するための目安として、ぜひこの計算方法をインプットしてください。
1. なぜ自社株評価が必要なのか?
自社株の評価は、様々な場面で必要となります。
- 事業承継: 相続税や贈与税の計算基準となるため、承継時の税負担を把握するために不可欠です。
- M&A(会社売却・買収): 売却価格や買収価格を交渉する際の目安となります。
- 株主間の売買: 退職する役員や社員から株式を買い取る際、あるいは新規の株主に譲渡する際の価格決定の根拠となります。
- 資金調達: 新たな投資家からの出資を受け入れる際の株式発行価格の目安となります。
このように、自社株評価は会社のオーナーシップや経済的価値に関する重要な判断に直結します。
2. 自社株評価の基本:「純資産価額」と「収益力」
税務上の自社株評価にはいくつかの複雑な方法がありますが、その根底にあるのは大きく分けて以下の2つの考え方です。
- 純資産価額: 会社が「今、いくらの資産を持っているか」という視点。会社を清算した場合に、株主が受け取れる金額に近いイメージです。
- 収益力: 会社が「将来、いくらの利益を生み出せるか」という視点。会社の将来性や稼ぐ力を重視します。
簡易計算では、このどちらか、あるいは両方を簡略的に捉えて計算します。
3. 誰でもできる!自社株評価の「簡易計算方法」2選
ここでは、専門知識がなくても比較的容易に計算できる2つの簡易評価方法をご紹介します。
簡易計算方法1:純資産価額方式(簡略版)
最もシンプルで、誰でも計算しやすい方法です。会社のバランスシート(貸借対照表)があれば計算できます。
(1) 計算の考え方
- 会社の「資産の合計額」から「負債の合計額」を引くと、「純資産(自己資本)」が算出されます。これは、会社が保有する財産から、返済義務のある借金を差し引いた、株主が最終的に受け取れる価値の目安となります。
- この純資産の合計額を、発行済株式総数で割ることで、1株あたりの純資産価額が計算できます。
(2) 準備するもの
- 直近の貸借対照表(バランスシート)
(3) 計算式
1株あたり評価額 = (資産の合計額 - 負債の合計額) ÷ 発行済株式総数
(4) 計算例
- 資産の合計額:2億円
- 負債の合計額:1億円
- 発行済株式総数:10,000株
1株あたり評価額 = (2億円 - 1億円) ÷ 10,000株 = 1億円 ÷ 10,000株 = 10,000円/株
(5) この方法のメリット・デメリット
- メリット:
- 計算が非常に簡単で、誰でもすぐにできる。
- 会社の客観的な財産状況を把握できる。
- デメリット:
- あくまで帳簿上の数字を使うため、資産の含み益・含み損(特に不動産など)が反映されない。例えば、簿価1億円の土地が現在の時価では2億円の価値がある場合、その含み益が評価額に反映されません。
- 会社の将来の収益力やブランド力、技術力といった無形資産が全く考慮されないため、実態と乖離する可能性がある。
簡易計算方法2:年買法(ねんばいほう)
会社の将来の収益力を重視した評価方法です。よりM&Aの価格決定に近い考え方と言えます。
(1) 計算の考え方
- 会社の年間の利益に、何年分の利益を乗じるかという「年数(買収年数)」を掛け合わせて評価額を算出します。
- この「年数」は、業界や会社の安定性によって感覚的に設定するため、より簡易的な目安となります。
(2) 準備するもの
- 直近の損益計算書(営業利益、経常利益、当期純利益のいずれか)
- 直感的な「買収年数(X年)」 ※後述
(3) 計算式
1株あたり評価額 = (年間利益 × 買収年数X) ÷ 発行済株式総数
(4) 計算例
- 年間利益(例:経常利益):3,000万円
- 買収年数X:5年(業界や会社の安定性から判断)
- 発行済株式総数:10,000株
1株あたり評価額 = (3,000万円 × 5年) ÷ 10,000株 = 1億5,000万円 ÷ 10,000株 = 15,000円/株
(5) この方法のメリット・デメリット
- メリット:
- 会社の将来の収益力という、M&Aにおいて重要な要素を反映できる。
- 比較的計算が簡単。
- デメリット:
- 「買収年数X」の設定が恣意的(主観的)になりやすいため、評価額の信頼性が低い。この年数が1年変わるだけで評価額が大きく変動するため、注意が必要です。
- あくまで利益のみを考慮するため、会社の純資産や負債状況が考慮されない。
- 単年度の利益に依存するため、突発的な利益や損失があった場合に評価が歪む。
4. 簡易計算の注意点と「正式な」自社株評価の重要性
今回ご紹介した簡易計算は、あくまで「ざっくりとした目安」を知るためのものです。
4-1. 簡易計算は税務申告には使えない
これらの簡易計算方法は、税務署に提出する相続税や贈与税の申告には使用できません。税務上の正式な自社株評価は、国税庁が定める**「財産評価基本通達」**に基づいて、より複雑な計算方法(類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式など)を適用して行われます。
- 正式な評価の複雑さ:
- 会社の規模(大会社、中会社、小会社)や、株主の種類(同族株主か、少数株主か)によって適用される評価方法が異なり、複数の評価方法を組み合わせて計算する場合もあります。
- 不動産などの資産は、帳簿価額ではなく相続税評価額(時価に近い概念)に修正して評価します。
- 会社の負債や法人税等相当額も考慮されます。
- 過去数年の利益をならしたり、将来の収益予測を織り込んだりするなど、より詳細な分析が必要です。
4-2. 「正式な」自社株評価は税理士に依頼すべき
相続税や贈与税申告のための自社株評価は、必ずM&Aや事業承継に詳しい税理士に依頼しましょう。
- 正確な税額の把握: 誤った評価は、過少申告による追徴課税や、過大評価による納税資金の無駄につながります。
- 節税対策の提案: 事業承継税制の適用支援や、株価引き下げ対策など、合法的な節税策を提案してもらえます。
- 税務署への説明責任: 税務調査が入った際にも、税理士が作成した評価書であれば、その根拠を税務署に説明できます。
4-3. 簡易計算の活用場面
それでは、簡易計算はどのような場面で役立つのでしょうか。
- M&A検討の初期段階: 専門家への相談前に、「だいたいこのくらいの価値があるのか」という目安を知りたい時。
- 事業承継の漠然とした検討: 将来的な承継を考える上で、おおよその税金や資金準備のイメージを掴みたい時。
- 社員への説明: 社員にMBO(マネジメント・バイアウト)を打診する際など、最初の会話のきっかけとして目安の数字を伝える時。
5. まとめ:簡易計算は「第一歩」、本番は「専門家」と
自社株評価の簡易計算方法は、経営者が自社の価値を大まかに把握するための便利なツールです。これにより、M&Aや事業承継といった大きな経営判断の第一歩を踏み出すことができます。
- 純資産価額方式(簡略版): バランスシートから「資産合計-負債合計」で純資産を算出し、発行済株式総数で割る。会社の現在の財産状況の目安。
- 年買法: 年間利益に「買収年数X」を掛けて評価する。会社の将来の収益力の目安。
- どちらも目安: あくまで簡易計算であり、税務申告には使えない。
- 正式評価は複雑: 税務上の自社株評価は、会社の規模や株主の種類に応じて複数の方法を組み合わせて計算する。
- 専門家は必須: 正確な自社株評価と税金対策のためには、M&Aや事業承継に詳しい税理士への依頼が不可欠。
簡易計算で大まかな自社株の価値を把握したら、次は躊躇せず、M&Aや事業承継の専門家に相談し、正式な企業価値評価と、あなたの会社にとって最適な事業承継戦略を立ててもらいましょう。それが、会社の未来を確実に、そして有利な形でつなぐための最も賢い道です。