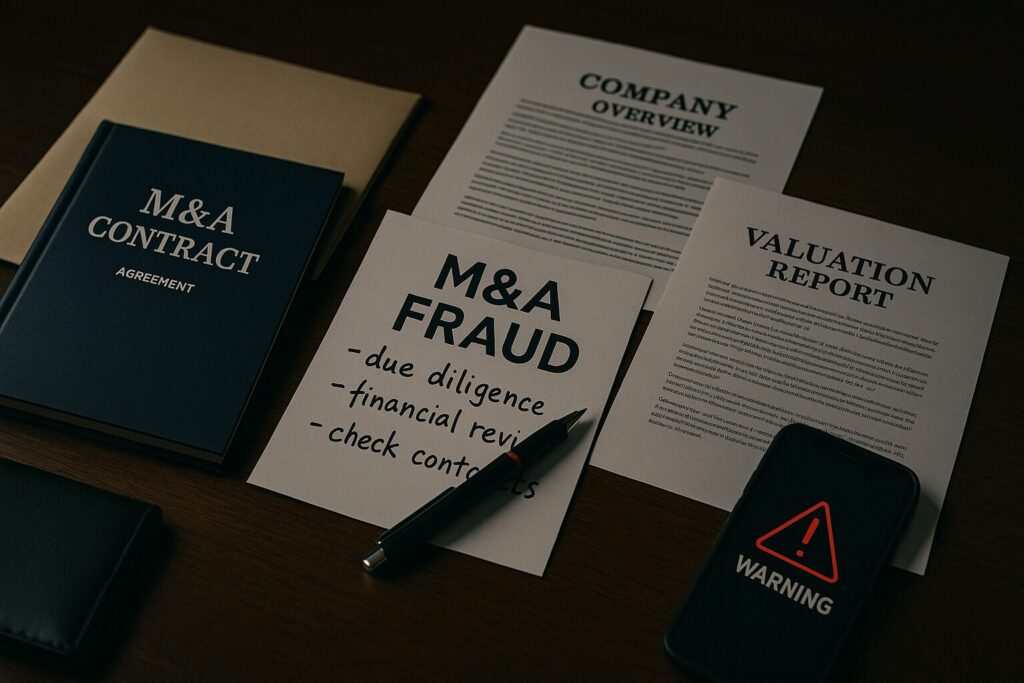1. はじめに
近年、中小企業や地方企業においても**M&A(合併・買収)**が急速に普及し始めています。事業承継や人材確保の手段としてM&Aを検討する企業が増え、仲介会社やアドバイザリーも多数参入するようになりました。一方、その流れに便乗する形で、M&A詐欺と呼ばれる不正行為や悪質な事例も散見されるようになってきています。
たとえば「高値で買いますよ」と甘い言葉で近寄ってきた業者が、契約前に着手金を騙し取ったり、買い手を見つけるフリだけして何も動かなかったり。あるいは買収側が誇大な事業計画を掲げて、売り手を騙してしまうケースも。ここ1~2年の間に報道される事例もいくつかあり、経営者やオーナーに大きな不安を与えています。
M&A詐欺の被害に遭うと、会社が受けるダメージは資金だけでなく、経営者の精神的負担、社員や取引先との関係悪化など、多大な影響を及ぼしかねません。今回は、最新のニュースを引き合いにしながらM&A詐欺の実態や手口を解説し、さらに「騙されないために知っておくべきチェックポイント」や「対策のヒント」を詳しくご紹介します。
M&Aを成功させるには、正しい知識と慎重なリスクマネジメントが欠かせません。これを機に、皆さんもぜひ“騙されない”準備をしておいてください。
2. なぜM&A詐欺が増えているのか?背景と現状
2-1. 中小企業の事業承継ニーズが急増
高齢化による後継者不足が深刻化し、多くの地方企業が事業承継問題を抱えています。そこでM&Aによる外部への売却を検討するケースが増えた結果、「M&A仲介を名乗る会社」が売り手企業に近づく事例が急増しています。
- 売り手企業としては、「うちの会社を高値で買ってくれる人がいるならありがたい」と思いがち
- しかし、その真偽を十分に確かめることなく、着手金や顧問料を払ってしまい、結局買い手が見つからないなどの詐欺行為につながる
2-2. 買い手サイドも注意が必要
売り手だけでなく、買い手側にも詐欺リスクがあります。たとえば「実態のない企業」や「巨額負債を隠している会社」を魅力的に見せかけ、高値で売りつけようとする詐欺師が潜んでいるかもしれません。買い手は「いい案件を見つけた!」と飛びついてしまい、後で重大な債務や法的リスクを背負う羽目になる可能性があります。
2-3. インターネットやSNSで偽情報が拡散
SNSやオンラインマッチングプラットフォームでM&Aの相手探しが行われる時代になりましたが、それを悪用して「都合の良いプロフィールを偽装」「事業計画を捏造」などを行う詐欺も増えています。遠方の相手とは直接会わずに交渉を進めることも多く、騙しやすい環境が整っていると言えるでしょう。
3. 近年報道されたM&A詐欺の事例
3-1. 「高値で買います」と言った業者が途中で失踪
最近あったニュース(2022~2023年頃)で取り上げられたケース:
- 地方のオーナー経営者が、事業承継のために会社を売ろうと考えていた
- 見知らぬ仲介会社から突然連絡が来て、「海外投資家があなたの会社に興味あり。数億円で買いたいそうだ」と言われ、着手金や顧問料を払い込んだ
- ところがしばらくして仲介担当が失踪、投資家も架空の存在だった
被害者の証言によれば、「こんな高値で売れるなら」と舞い上がり、契約書類の内容をろくに確認せずにお金を払ってしまったとのこと。M&A成功の見込みが全くないまま、着手金だけ巻き上げられてしまった事例として報道されました。
3-2. ファンドを名乗る集団が偽装書類を提示
あるケースでは、ファンドや投資家グループを名乗る組織が「あなたの会社に出資し、経営を一緒にやりたい」と近づき、事業計画書や投資契約書を提示。しかし、よく見ると会社名や代表のサインが偽造されていたといった事件が判明。
結局、その書類を信じてしまった企業は出資金を期待して設備投資を拡大し、最終的に資金繰りの悪化に陥ったという報道がありました。
3-3. 中古住宅の不正売買で経営主体を偽装
M&Aとは直接関係ないように見えますが、不動産の所有権や企業名義を偽装し、大手企業の子会社を騙ることで信用を得る詐欺が報道された例もあります。M&A取引でも、企業の実体を偽装したり、株主構成を偽って買い手を呼び込むという似た手口が考えられます。
4. M&A詐欺の典型的な手口
4-1. 着手金・顧問料の詐欺
一番多いのが着手金詐欺です。仲介会社やコンサルを名乗る業者が「すぐに買い手が見つかる」「高値で売れる」と謳い、着手金数十万~数百万円を請求。契約後、実質何も動かずに音信不通になったり、「まだ時間がかかる」と先延ばしされ、最終的に逃げられるケースがあります。
4-2. 価格吊り上げで期待感を煽り、途中で厳しい条件を押し付ける
売り手に「あなたの会社の価値は1億円以上あります」と高額査定を提示して興味を引き、契約を結んだ後、「やはりDD結果から債務リスクがあり減額となる」「仲介報酬率を上げる」などの不当な要求をするパターン。売り手は既に他社との交渉ルートを断っているため、泣く泣く応じるという事態になりがち。
4-3. 架空の買い手・売り手を装う
この手口は連絡先やプロフィールを巧妙に作り込み、「こんなに魅力的な企業がありますよ」「海外投資家が大きく投資してくれますよ」と見せかける。書類やサイトも偽造しており、実在しない企業や投資家を演じることもある。
結果、**買い手(または売り手)**は多額の手数料を前払いしつつ、いつまでも相手と進展しない。
4-4. 関係者を抱き込んで外堀を固める
悪質な例では、弁護士や会計士、仲介会社の担当者もグルになって詐欺を行うことがあります。書類作成に専門家の名前が使われると信用度が増すため、被害者が深く疑わずに契約してしまうのです。
社内で法的知識が薄い経営者は「弁護士が関わっているなら安心」と思いやすいですが、事務所名や資格証明の真偽を確認しないと危険です。
5. M&A詐欺を防ぐためのチェックポイント
5-1. 異常に高い評価やスピードを謳う業者に要注意
「通常なら数カ月かかるM&Aを1カ月で終わらせる」とか、「時価の倍で買い手が見つかる」といった非現実的な甘い言葉を安易に信じるのは危険です。M&Aは慎重な調査や交渉を要するプロセスであり、超短期で成約するのは極めて稀。やたら高値を提示されたら、冷静に「なぜそこまで高評価なのか」を突き詰めましょう。
5-2. 着手金を低く抑えて成果報酬型を基本とするか
着手金があっても構いませんが、何十万~何百万という大きな金額を最初に要求されるなら要注意。その代わりに成功報酬(クロージング後)で支払う形をメインとしている会社も多いです。もし高額な着手金を求められるなら、その根拠や内訳を細かく確認しましょう。
5-3. デューデリジェンスは第三者の専門家をしっかり入れる
買い手側の場合、売り手企業を調べるデューデリジェンスを仲介会社任せにすると、詐欺リスクが高まります。可能であれば自社が契約する弁護士・会計士を起用し、別途チェックを依頼すると安心です。
売り手側でも、相手が本当に資金力を持ち、実在するのかなどの調査を疎かにしないように。
5-4. 契約書を熟読し、社内外の専門家に相談
M&A詐欺の多くは、「契約書に書かれている条項が実は売り手・買い手に不利だった」という形で発覚します。面倒がらずに契約書や条文を細部まで確認し、不明点があれば弁護士や公的支援機関(商工会、事業引継ぎセンターなど)に相談しましょう。
5-5. ネットやSNS情報だけに頼らない
SNSで良さそうな仲介会社を見つけても、その情報が本物かはわかりません。実際に面談し、事務所を訪問し、担当者の経歴や会社の実態を見極めることが大切です。ネットの口コミは操作されている可能性も否定できないので、複数の情報源を当たるようにしましょう。
6. もし被害や違和感を感じたらどうする?
6-1. 速やかに交渉ストップし、法的助言を受ける
「これは怪しい」と思った時点で、一旦交渉を中断し、法的な専門家に相談するのが賢明です。やりとりのメールや契約書などの証拠を保全し、詐欺の可能性が高ければ警察や消費者センター、弁護士などに報告を。
手数料の返還を請求する場合でも、時効や証拠不十分で泣き寝入りしないよう、早めのアクションが必要。
6-2. 金銭面のダメージを拡大させない
詐欺業者は、途中で「追加で費用が必要だ」と言ってさらにお金を請求する可能性があります。少しでも怪しいと思ったら、「これ以上支払うのは待ってほしい」と明確に意思表示し、支出を食い止めましょう。
また、会社の資金繰りや経営計画に悪影響が及ばないよう、銀行や税理士にも状況を共有し、再建策や防衛策を考えるのがよいです。
6-3. 公的支援機関や業界団体への相談
中小企業庁の事業引継ぎ支援センターや、地元の商工会・商工会議所などに相談すれば、M&Aに詳しい専門員の助言を得られることもあります。また同業界の団体がM&Aに関する相談窓口を設けている場合もあるので、同業の先輩経営者やネットワークを活用するのも有効です。
7. まとめ:騙されずにM&Aを成功させるために
M&Aは企業の将来を大きく左右する行為であり、詐欺のリスクが存在するのも事実です。M&Aは会社を大きく変え得るビジネスチャンスですが、詐欺の存在を認識し、冷静なリスク管理を行うことが不可欠です。
M&A仲介会社やアドバイザリーとの関係を築く中で「コミットラインを明確に」「費用対効果をチェック」「不審な点があれば即座に対処」という姿勢を常に持ち続けることで、正しいM&Aを実現し、会社の将来をより良い方向へ導くことができるでしょう。