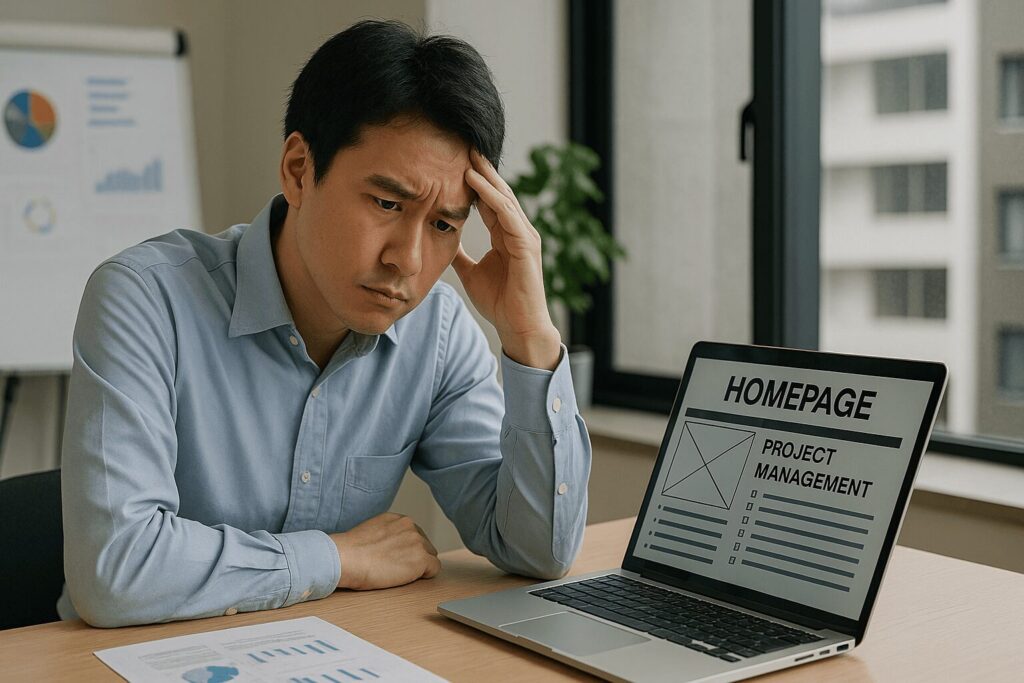はじめに:なぜホームページ制作は「事故」が起きやすいのか?
ホームページ(以下、Webサイト)の制作やリニューアルにおいて、「想定よりスケジュールが大幅に伸びた」「完成したものがイメージと違った」「追加費用が発生してしまった」など、いわゆる“事故”にあたるトラブルを耳にしたことはありませんか?経験したことのある方もいるかもしれません。実際、Web制作の現場ではさまざまな原因でプロジェクトが迷走し、苦い経験をするケースが少なくありません。
- 要件定義が曖昧なまま走り出す
- スケジュール管理がずさんで、いつの間にか間に合わない
- デザインや機能要望が後出しで増え、工程が破綻
- 社内意思決定が途中で変わり、作り直しになる
こうした“事故”の原因の多くは、プロジェクトの進め方やコミュニケーション、そして合意形成の方法に起因します。では、逆に考えると「事故らないプロジェクト」にはどのような特徴があるのでしょうか?本記事では、“事故らないホームページ制作プロジェクトの特徴10選”を取り上げ、それぞれのポイントと実践のヒントを解説していきます。
それでは、順番に見ていきましょう。
1. 明確な目的とゴール設定がある
1-1. ホームページ制作の“目的”とは?
事故らないプロジェクトの大前提として、まず「なぜホームページを作る(リニューアルする)のか?」が明確になっていることが挙げられます。ここでいう目的とは、単に「古くなったサイトをきれいにしたい」「アクセス数を増やしたい」という曖昧なものではなく、事業目標やマーケティング戦略と直結した具体的な指針です。
- 例:新規顧客獲得のために、問い合わせ数を半年後までに○倍にする
- 例:採用活動強化のため、採用ページ経由の応募数を年間○人以上にする
このように、Webサイト制作のゴールを数値目標や達成したい状態としてしっかり定義しておけば、デザインや機能、コンテンツ制作において「本当に必要かどうか」を判断する基準になります。
1-2. 目的とゴールを社内外で共有する重要性
目的とゴールが明確になっても、それが関係者全員にきちんと共有されていないと意味がありません。たとえば、経営者は「採用サイトとして機能させたい」と思っていても、現場レベルでは「製品PRのためにリッチなコンテンツを作る予定」と方向性がずれているケースがあると、後々コンフリクトが発生しやすいです。
したがって、プロジェクト開始時に経営層・担当部署・外部制作会社などの参加者全員で目的を言語化し、合意形成しておくことが「事故らない」ための第一歩といえるでしょう。
2. 要件定義・サイト構造の早期合意
2-1. 要件定義で“やりたいこと”を漏れなく整理
ホームページ制作でよくある事故の一つに、「あとから要求が出てきてスケジュールが崩壊」というものがあります。最初に決めていた機能やページ数を超えてしまい、工数が膨れ上がるというパターンですね。
これを防ぐには、要件定義の段階でサイトの構造、ページ内容、必要な機能などをしっかり洗い出すことが重要です。サイトマップを作成し、各ページの役割や掲載コンテンツを明確にしておきましょう。機能要件がある場合は、どんな処理をどの画面で実行するかをできるだけ具体的に書き出すことが大切です。
2-2. サイトマップ・ワイヤーフレームの早期策定
要件定義を進めたら、それをサイトマップやワイヤーフレームに落とし込んで、全体像をビジュアル化します。サイトマップはページ同士の階層構造を示し、ワイヤーフレームは各ページのレイアウトや要素配置をラフな形で示すものです。
これらをプロジェクトの初期段階で合意できれば、「こんなページも作るべきだった」「このページはもっと情報量が必要だ」という後出し要望が減り、最初のスケジュール通りに進行しやすくなります。
3. 社内外の役割分担を徹底している
3-1. 「誰が何を担当するのか」を明確化
大規模なホームページ制作やリニューアルになると、関わる人が増えすぎて責任や役割が曖昧になることがあります。結果として、決めなければならないことが山積みになる一方、「それはどこが決めるの?」と作業がストップする事故が起こりやすいのです。
これを防ぐためには、社内・社外の担当を明確化することが必須です。たとえば、以下のように区分します。
- プロジェクトマネージャー(PM):全体進行管理や納期調整を行う
- 社内決裁者:重要事項の最終OKを出す(経営層・上層部など)
- デザイン担当(制作会社側):ワイヤーフレームの具体化、ビジュアルデザイン
- システム開発担当(制作会社 or 外部ベンダー):CMSや予約機能などの実装
- コンテンツ(文章・画像・動画)担当(社内 or 外部ライター):テキストや写真素材の準備
さらに、細かなパーツごとに「画像撮影は社内で行うのか、外注するのか」「原稿チェックは誰が最終責任を持つのか」など、スコープを明確に仕切っておくことが大切です。
3-2. プロジェクトオーナーの重要性
大規模プロジェクトになればなるほど、社内に“オーナーシップ”を持った人が不在だと迷走しがちです。各部署や外部スタッフがバラバラに動くと、「決裁を取るまでに何日もかかった」「対立意見が収束しないままズルズル…」という事態になりやすいです。
そこで、プロジェクト全体をリードできる社内の“責任者”を明確に指名しておくことがポイント。プロジェクトマネージャーを制作会社に任せている場合でも、社内側の窓口となる“オーナー”が社内調整を素早く進められるようにしておくと、意思決定のスピードが上がり事故を防ぎやすくなります。
4. 社内に決裁フロー・ガイドラインを準備している
4-1. 決裁フローが整備されていないと起こる悲劇
ホームページ制作における事故の典型例の一つに、「社内決裁が進まず、スケジュールが大幅に遅延する」というものがあります。デザイン案や機能仕様を提示しても、上司や役員クラスの承認を得るまでに何週間もかかるケースです。ときには、承認直前で“やっぱりこう変えた方がいい”という指示が入ることもあり、制作会社からするとたまったものではありません。
- 例:
- デザイン案を4案出したが、社長だけでなく副社長、さらに部長・課長なども口を出し始め、最終決定まで1か月かかった
- 提案を一度承認したのに、後日経営会議でひっくり返された
こうした事故を起こさないためにも、「どの段階で誰が承認を出すのか」というフローを事前に明確にしておくことが大切です。
4-2. 社内ガイドラインの存在がプロジェクトを円滑にする
会社によってはブランドガイドラインやデザインガイドライン、コピーライティングの基準などが存在するかもしれません。これらがきちんと整備され、かつプロジェクトメンバーが共有できていると、デザイン案や文章表現で揉めることが減ります。
- 例:
- コーポレートカラーやロゴ使用ルールが定義されている
- SNS運用方針や文体のガイドラインが整っている
もしガイドラインがない場合は、初期段階で制作会社と一緒に基本トーン&マナー(T&M)を策定すると、後々のブレが起きにくいでしょう。
5. 定例ミーティングと共有ドキュメントが充実
5-1. 定例ミーティングで常に進捗を把握
Web制作プロジェクトはデザイン、コーディング、コンテンツ準備など複数の工程が並行して進むため、どこか一つでも遅延が起こると全体に波及します。そこで、定期的なミーティングや進捗報告会を開催し、各メンバーの状況を把握し合うことが不可欠です。
- 週1回の定例ミーティング:進捗状況や課題を共有し、問題があれば早期に対処
- 担当者ごとのタスク一覧:期日と完了状況を可視化し、リマインドを行う
こうした進行管理を怠ると、「デザインができていないのに原稿が納品されず放置」「CMS実装が終わらないのにページ構成が勝手に変わった」などの齟齬が発生し、“事故”に繋がりやすくなります。
5-2. ドキュメントやツールの活用で情報を一元化
事故を防ぐためには、プロジェクトのあらゆる情報を一元管理し、誰でもすぐに確認できる状態にすることが望ましいです。最近では、GoogleドライブやNotion、Backlog、Redmine、Trelloなど、プロジェクト管理ツールやドキュメント共有ツールが多様に存在します。
- 導入メリット:
- メールの行き違いが減る
- 最新版の仕様書やデザイン案がすぐに参照できる
- コミュニケーションログが残り、後から見返せる
大切なのは、ツールを決めても使いこなせないと意味がない点です。最初に関係者で「どのツールで、どの資料を管理するか」を決め、マニュアルを簡単に作っておくとスムーズに運用できます。
6. デザインコンセプトが全メンバーに浸透している
6-1. デザインの“好き嫌い”を超えるために
ホームページ制作において、デザインに関する主観的な意見の対立は起こりがちな事故要素です。特に経営者や役員の好みが強く反映される場合、デザイナーから見ると「理にかなっていない変更」に思えても、現場では断れずに修正を繰り返してしまうケースがあります。
これを回避するには、デザインコンセプト(トンマナ)をあらかじめ策定し、そこに照らして判断する仕組みが必要です。
- 例:
- ターゲット層は若年女性が中心なので、配色やビジュアルはポップ&カラフル
- 高級感や専門性を重視するサイトなので、落ち着いた色味や洗練されたレイアウト
こうした方針が明確になっていれば、「社長が青色が好きだから」「このイラストを大きくしたい」といった“個人の好み”によるリテイクを最小化できます。
6-2. デザイン案の提示とフィードバックのコツ
デザインをチェックするときは、いきなり完成形のビジュアル案を提示するよりも、最初はワイヤーフレームやコンセプトボードでイメージをすり合わせるのが定石です。
- ステップ:
- デザイナーが方向性となるサンプルや参考事例を複数提示
- キービジュアルや色・フォントなどを概略レベルで合意
- ラフデザイン→詳細デザインへと段階的に仕上げていく
このプロセスを適切に踏むと、大幅なデザイン変更が発生しにくくなり、“こんなはずじゃなかった”事故が防げます。
7. コンテンツ制作のスケジュール管理を厳格に行う
7-1. “コンテンツが揃わない”という大きな落とし穴
実はホームページ制作で最も多いトラブル原因として、「記事や写真、動画などのコンテンツがスケジュール通りに揃わない」が挙げられます。社内で原稿を作る場合、日常業務の合間に執筆するため後回しにされてしまい、納期に間に合わなくなるパターンです。
- 典型的な事故:
- 原稿が来ないのでデザインが止まり、納品日が1~2か月遅延
- 写真素材が不足しているため、仮のダミー写真で進行し、後から大量リテイク
7-2. コンテンツ担当者と納期の明確化
これを防ぐには、コンテンツの担当者(執筆者)や撮影担当、納品日を明確に定め、しっかりタスク管理する必要があります。可能であれば、外部ライターやカメラマンを活用しても良いでしょう。
- ポイント:
- どのページに何文字程度の文章を載せるか、どんな画像が必要かをサイトマップ段階で決める
- 執筆者に必要な情報や資料を早めに共有する
- 制作会社と連携し、原稿フォーマット(見出しや文字数、画像の位置など)を事前に取り決める
こうしておけば、制作会社側は仮デザインを進めながらも「何日に何のコンテンツが届く」と把握できるため、事故のリスクがぐっと下がります。
8. テスト・検証フェーズで妥協しない
8-1. マルチデバイス・マルチブラウザの動作確認
ホームページが完成に近づくと、つい安心してテストや検証を疎かにしてしまう場合があります。しかし、**スマートフォンやタブレット、複数のブラウザ(Chrome、Safari、Firefox、Edgeなど)**で問題なく表示・動作するかは非常に重要なポイント。
- よくある事故:
- PCでは見た目が整っているが、スマホで表示が崩れている
- ある特定のブラウザで動きがおかしい
- 画面解像度が異なるデバイスでレイアウトがズレる
これらの不具合をローンチ直前に発見すると、修正コストが高くなってしまいます。事故らないプロジェクトでは、早めにテスト環境を用意し、段階ごとに動作確認を行う習慣が根付いています。
8-2. フィードバックラウンドの設定
テストやプレビューに対するフィードバックの回数をあらかじめ設定しておくのも事故防止につながります。無制限に修正要望を受け付けてしまうと、終わりが見えなくなることがあるからです。
- 例:
- 第1ラウンドでデザインやレイアウト関連の修正点をまとめて提出
- 第2ラウンドで残っている機能面や文言修正を一括で提出
- 追加要望は別途見積もりとスケジュール検討を行う
こうしたルールを決めておくと、後出し修正を最小限に抑え、スケジュールを守りやすくなります。
9. 適切なスコープコントロールができる仕組み
9-1. スコープクリープ(要求の膨張)を防ぐ
ホームページ制作の現場では、進行中に新たな機能要求やデザイン変更が出てくる“スコープクリープ”がトラブルの元になりがちです。「やっぱり問い合わせフォームにチャット機能が欲しい」「サービス紹介ページを増やしてほしい」といったリクエストがどんどん追加されると、コストと納期が膨れ上がり、最悪の場合プロジェクトそのものが破綻しかねません。
9-2. 追加要望への対応プロセス
事故らないプロジェクトでは、追加要望や修正要望が出た時の対応フローが明確に定義されています。たとえば、以下のステップを踏む仕組みを作ると良いでしょう。
- 要望提出:誰がどのような要望を出したのか、文書で残す(メールやチケット管理システムなど)。
- 影響調査:制作側が要望を実現するために必要な工数や費用、納期への影響を試算する。
- 合意形成:追加費用や納期延長が必要なら、依頼元と協議して合意する。合意が得られない場合は見送る、または次フェーズへ持ち越す。
- 仕様書の更新:決定事項を公式なドキュメントに反映し、プロジェクトメンバー全員へ通知する。
こうしたフローがなければ、口頭ベースで安易にOKを出してしまい、後になって「そんなに大変だとは思わなかった」「予算内でやってくれると思っていた」といった認識違いが起こります。
10. ローンチ後の運用体制まで設計している
10-1. ホームページは作って終わりではない
実は、ホームページ制作が無事にローンチしても、それでプロジェクトが完全に終わるわけではありません。運用や保守フェーズがスタートし、以下のような課題が継続して発生します。
- コンテンツの更新:最新情報やニュースを掲載し続ける
- セキュリティ対策:CMSやプラグインのアップデート、サーバーの保守
- アクセス解析と改善:Google Analyticsやヒートマップなどで効果測定し、ABテストを実施
ここを怠ると、せっかく立ち上げたサイトが放置状態になり、検索順位が落ちたり、サイト内の情報が古くなったりしてユーザーの信頼を損ねる原因になります。
10-2. 運用担当の配置と更新手順
事故らないプロジェクトでは、ローンチの時点で運用体制やスケジュールを策定しているケースが多いです。具体的には以下のような内容を決めます。
- 運用担当者:誰が日々のコンテンツ更新や問い合わせ対応を行うのか
- 更新頻度と手順:週次更新、月次更新などのルールを決め、必要な権限やCMSのマニュアルを整備
- 保守契約の範囲:外部制作会社に保守を依頼する場合、どこまで対応してもらうのか(バグ修正、デザイン変更など)
- 定期レポート:アクセス解析や目標KPIの達成状況をどの周期でレポートするか
こうした仕組みがあれば、ローンチ後にバタバタすることなく、長期的にWebサイトの価値を高めていけるでしょう。
まとめ:事故らないWeb制作を支える10の特徴
ホームページ制作は、社内外の多くの人が関わる一大プロジェクトです。そのため、些細なコミュニケーションミスや決裁フローの遅延、コンテンツ不足などが重なると、納期遅延や予算オーバー、満足度の低い仕上がりといった“事故”に繋がりやすくなります。
今回ご紹介した「事故らないホームページ制作プロジェクトの特徴10選」を振り返ると、以下のポイントが見えてきます。
- 明確な目的とゴール設定がある
- Web制作のゴールが事業目標とつながっており、関係者が共有している
- 要件定義・サイト構造の早期合意
- サイトマップやワイヤーフレームで全体像を最初に固め、後出し要望を減らす
- 社内外の役割分担を徹底している
- プロジェクトオーナー、制作会社、執筆者などの担当範囲を明確に決める
- 社内に決裁フロー・ガイドラインを準備している
- デザインやコンテンツを誰がいつどのように承認するかを明確化
- 定例ミーティングと共有ドキュメントが充実
- プロジェクト管理ツールや定例会議を活用し、進捗や課題を可視化
- デザインコンセプトが全メンバーに浸透している
- 個人の好みでリテイクが頻発しないよう、方向性を事前に一致させる
- コンテンツ制作のスケジュール管理を厳格に行う
- 原稿・写真・動画が期日通りに揃うよう、担当者と納期を徹底
- テスト・検証フェーズで妥協しない
- デバイスやブラウザごとの動作確認を早め・念入りに行う
- 適切なスコープコントロールができる仕組み
- 追加要望が出た場合の費用・納期への影響を評価し、正式に合意を取る
- ローンチ後の運用体制まで設計している
- 作りっぱなしにせず、更新・保守・改善サイクルを確立
すべてを完璧に実行するのは難しいかもしれません。しかし、これらのポイントを意識するだけでも、“なんとなく進めていたら大惨事に…” というリスクを大幅に減らせるはずです。
ホームページは企業の顔となる重要な媒体です。せっかくリニューアルを行うなら、十分に時間と労力をかけて準備し、目的達成につながる良質なサイトを完成させたいですよね。ぜひ本記事を参考に、事故らないWeb制作プロジェクトを実現してみてください。