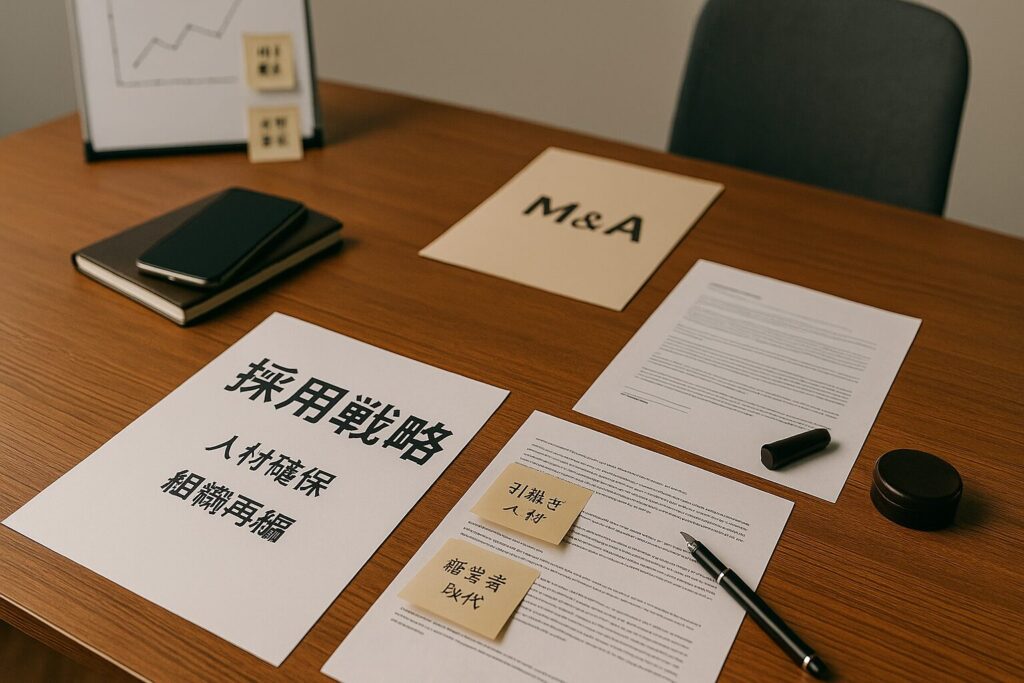1. はじめに
地方企業の人材不足が深刻な問題として浮上して久しい昨今。今後も少子高齢化が続き、地方の若年層人口が減少し続けることを考えれば、その影響はますます拡大していくと見られています。求人をかけても応募が集まらない、採用してもすぐ辞めてしまう――そんな悩みを抱える経営者の声を耳にする機会も多いでしょう。
一方で、都会の新興企業などでは比較的容易に若い人材を確保できているケースもあります。なぜなら、都市部には充実したインフラや多様な仕事の選択肢があり、“若い世代にとっての魅力”が詰まっているからです。では、その若い人材がすでに属している企業ごと買収する――いわゆるM&A(合併・買収)を行うことで、人材不足の解消につなげることは可能なのでしょうか?
2. なぜ地方企業の人材不足は深刻なのか
2-1. 少子高齢化と若年層の都市部流出
地方では、元々の人口減少に加え、特に若い世代が学業や就職を機に都市部へ流出する傾向が顕著です。その結果、地域内の企業が必要とする労働力はますます不足し、「地元で十分な数の新卒や中途を確保できない」という状況に陥っています。
2-2. Uターン・Iターンのハードルの高さ
近年、一部で「地方移住ブーム」が取り上げられたり、リモートワークが普及したりしているものの、実際にUターンやIターン就職(転職)のハードルは依然として高いです。地元に戻ったところで職種や給与面、生活インフラなどの条件が都市部と比べて魅力に欠ける場合、なかなか踏み切れないというのが実情でしょう。
2-3. 地域経済の停滞に伴う企業の厳しい状況
地方企業は、多くが中小規模であり、売上や利益が伸び悩む中で採用コストを確保するのも難しい現状にあります。さらに、十分な給与や福利厚生を用意できず、都会の企業との競争に負けてしまう――というケースも少なくありません。
3. 人材確保をめぐる新たな選択肢「M&A」
3-1. 従来の解決策:採用強化や外部支援の活用
これまで地方企業が人材不足を解消しようとする際、主な選択肢といえば以下のようなものでした。
- 採用広報やリクルーティングの強化:大学との連携、SNSや求人サイトでの情報発信
- ハローワークや人材紹介会社の利用:一定の応募者を集めるが、質の面や費用対効果に限界
- 自治体の移住支援策や地方創生プロジェクトへの参加:Uターン・Iターン希望者をターゲットにしたプログラム
しかし、これらを積極的に行っても、根本的な人口減少や都市部の魅力を覆すのは難しく、十分な人材が集まらないという声が後を絶ちません。
3-2. 新発想:「人がたくさんいる会社」を丸ごと買収する
ここで注目されているのが、M&Aによる人材確保という発想。つまり、既に豊富な人材を抱えている企業(例:都心部の新興IT企業など)を買収し、その企業を傘下に入れることで、優秀な人材をグループ企業の一員に迎え入れるのです。
具体的なシナリオとしては、地方企業が都心の企業を“東京支社”として運営する形を取ったり、新興企業の技術やサービスを取り込むことで本社の事業を強化したりすることが考えられます。採用で苦戦しているなら、「自前で人を採る」以外の手段を模索しても良いのではないか?――そういう議論が進んでいるのです。
4. M&Aで採用課題が解決できる理由
4-1. 既に在籍している人材をスライドで活用できる
M&Aによる買収を行うと、被買収企業の従業員はそのまま親会社のグループ社員として扱える可能性があります。これは、“頭数”を確保するという意味合いだけでなく、その企業が持つ特殊な技能やノウハウも獲得できる点で、大きなメリットです。
たとえば、地方の老舗メーカーが都内のテック企業を買収すれば、優秀なエンジニアやデザイナーがチームとして引き継がれる可能性があり、デジタル化や新規事業開発の人材不足を一気に解消できるかもしれません。
4-2. 企業ブランドやノウハウを一挙に吸収
被買収企業の人材だけでなく、その企業が築いてきたブランド力、顧客基盤、業務ノウハウなどをそっくり取り込むことができる点も魅力です。これにより、地方企業単独では難しかった新規市場への参入や商品開発が一気に進む可能性があります。
たとえば、ITベンチャーを買収して自社のIT部門として機能させることで、地方企業が抱える既存事業の効率化やDXが加速するケースもあるでしょう。
4-3. 相互補完で組織を強化
M&Aは、一方的に「大きい会社が小さい会社を飲み込む」だけではありません。地方企業側が都心企業を買収することで、相互の不足を補い合う関係が築けるかもしれません。
- 地方企業:資金力や長年の業界コネクション、安定した収益源などを提供
- 買収先の新興企業:若い人材や先進的な技術、都会での販路や文化を提供
このようにお互いの強みを掛け合わせれば、今までにないビジネスモデルや商品開発が期待でき、単なる“人材確保”を超えた相乗効果を狙えるのです。
5. M&Aによる人材確保のメリットと注意点
5-1. メリット
- 時間をかけずに人材を獲得できる
通常の採用活動では、募集から選考、内定、入社まで少なくとも数カ月~半年以上かかるのが一般的です。さらに、せっかく採用してもミスマッチで退職してしまうリスクは常にあります。しかし、M&Aなら既に業務に精通した人材チームを一挙に取り込めるため、即戦力として活躍を期待できる可能性が高まります。 - 新規事業やDXを加速できる
特にITや先端技術分野の人材不足は全国的な課題ですが、都会にはまだまだ優秀なエンジニアやデザイナーが存在する企業が多いです。それらを一括で迎え入れることで、ローカル企業が急速にデジタル化を進めたり、新規プロジェクトを立ち上げたりする「一気通貫のアプローチ」が可能になります。 - 買収先の顧客基盤やブランドイメージを活用
買収される企業が持つ顧客ネットワークや認知度を、そのまま地方企業のビジネス拡張に活かせる点は大きな魅力です。例えば、都心で有名なスタートアップを買収して、“東京支社”として運営することで、全国的な展開を図る一歩を踏み出すことができるでしょう。
5-2. 注意点・リスク
- 文化の統合が難しい
M&A後の統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)がスムーズに進まないと、組織文化の違いから社内トラブルや人材流出が起こるリスクがあります。特に地方企業と都会のベンチャー企業では、仕事の進め方や社内ルール、給与体系などが大きく異なるかもしれません。買収後のマネジメントに注力しなければ、せっかくの人材が辞めてしまう可能性があります。 - 投資コストが大きい
M&Aには多額の資金が必要になるケースが多く、地方の中小企業にとってハードルが高いのは事実です。買収後にも追加の投資が必要になるかもしれず、財務負担を軽視できません。投資対効果を十分に見極めることが欠かせないでしょう。 - 企業選定の難しさ
一口に「都会の新興企業を買収する」と言っても、そもそも売り手企業が求める条件(買い手企業の資金力や業種の親和性など)に合致しなければ成立しません。また、「この企業を買って本当にうまくいくのか?」という目利きが求められるため、M&Aの専門家のサポートや、入念なデューデリジェンスが必須です。 - 人材が必ず残るわけではない
M&A直後に、被買収企業の従業員が一斉に離職してしまうケースもあります。特に優秀な人材ほど、買収に伴う会社の方針変化を嫌って独立したり、ライバル企業に転職したりする可能性があるため、十分な説得や待遇面の検討が必要となるでしょう。
6. M&Aで採用課題を解決する際のポイント
6-1. ビジョンや目的を明確にする
M&Aをする際、「なぜ買収するのか?」という明確なビジョンを社内外に示すことが重要です。単に「人材が欲しいから」「成長したいから」という曖昧な理由だと、買収先企業の社員が「これからどうなるの?」と不安を抱きやすくなります。
- 「地方企業×都市部ベンチャー」で相乗効果を狙う新ビジネスを立ち上げる
- 自社のDX推進を加速し、新市場へ参入する
- 既存事業と補完し合う技術・サービスを拡充する
など、具体的なゴールを示すことで、買収先社員や自社社員のモチベーションが高まりやすくなるでしょう。
6-2. ポストM&Aのマネジメント(PMI)を重視する
M&Aが成立して終わりではありません。むしろそこからがスタートです。**PMI(Post Merger Integration:買収後の統合プロセス)**で組織融合を失敗すれば、期待したシナジーは得られないどころか、混乱だけが残ってしまう可能性があります。
- 給与や評価制度の統一・調整
- 組織構造の再編
- 社内コミュニケーションの活性化
- 既存社員と買収先社員の交流イベント
など、丁寧な統合作業が求められます。
6-3. 被買収企業のキーパーソンをしっかりキープ
M&Aの大きなメリットである“優秀な人材確保”を実現するためには、キーパーソンと呼ばれる中心人物に残ってもらうことが不可欠です。彼ら彼女らの離職を防ぐために、役員登用や特別報酬、将来のキャリアビジョンなど、買収後の処遇を十分に話し合うことが大切。
「M&Aされてしまったから、経営の自由度が失われた」というネガティブな感情を持たれないよう、共通のビジョンを持って一緒に成長できる関係を築く必要があります。
6-4. 専門家との連携やアドバイザリーの活用
M&Aは法務や財務、税務など、様々な専門分野が絡む複雑な取引です。地方企業が初めて取り組むには難易度が高いかもしれません。
そこで、M&Aの専門家(仲介会社やアドバイザリーなど)を活用することで、適切な売り手企業のリサーチ、買収プロセスの交渉や契約書作成、PMI支援などを一括サポートしてもらえる場合があります。費用はかかりますが、成功確率を高めるためには頼もしいパートナーとなるはずです。
7. 実際の事例(仮想シナリオ)
ここでは、簡単な仮想シナリオを通じて、地方企業がM&Aを活用して採用課題を解決するイメージを示します。
- 地方企業A社:地方都市にある老舗メーカー。高い技術力と安定した顧客を持つが、最近はデジタル化や人材不足で成長が停滞。若いIT人材を採用できず、DX推進に遅れが目立つ。
- 都会の新興企業B社:東京で急成長中のITベンチャー。優秀なエンジニアやプログラマーを多数抱えるが、資金繰りが苦しい面も。ビジョンはあるが安定性に不安を感じる社員が増えている。
A社は「社内デジタル化で生産性を上げたい」「新規サービスを開発し、海外市場にも進出したい」という目標を持つが、IT人材不足がネックになっている。
一方、B社は「安定した財務基盤で研究開発を続けたい」「短期的な売上目標に追われる日々から脱却したい」と考えており、ちょうど資金調達に苦労していた。
双方の利害が一致し、A社がB社を買収する運びとなる。買収後は、B社を東京支社として残し、B社社員は引き続き勤務地を変えず働く形に。A社はそこへDX投資を行い、B社の優秀な人材の力を借りながら地方本社の業務効率化や新規サービスの開発を行う。
結果として、A社は採用難を一気に克服し、数十人のエンジニアを取り込むことに成功。B社の社員にとっても、地元企業の資本注入により財務が安定し、じっくりと製品開発ができる環境が整う――というウィンウィンのシナリオが展開されるわけです。
8. まとめ:採用の概念を超えて「M&Aで人材確保」という選択肢
地方企業の採用課題は、単なる求人強化だけでは解決が難しくなってきています。若年人口の減少や都市部との競合など構造的な問題が重なり、思うように人が集まらないからです。しかし、そこで思考を転換し、「欲しい人材を持っている会社を買収してしまう」という戦略をとれば、一気に新しい道が開けるかもしれません。
もちろん、M&Aにはそれなりのリスクやコストが伴いますし、企業文化や人材の流出などクリアすべき課題は多々あります。それでも、従来のやり方だけでは解決しない頑固な採用難に直面している地方企業にとって、M&Aは有力な選択肢になり得るのです。
- 採用にかかる時間や労力を省き、優秀な人材チームを一括で確保できる
- 買収先企業のブランドやノウハウも活かせる
- 地方企業と都会の企業が相互補完できれば、新事業創出やDX推進が加速
ただし、M&Aが成功するかどうかは、買収後の統合プロセス(PMI)の成否や、キーパーソンをどう留保するか、双方のビジョンをいかに一致させるかにかかっています。M&Aを単に「採用の裏技」として使うだけではなく、「新たなビジネスモデルや企業成長のためのパートナーシップ」と捉えることが肝心でしょう。
「人材不足をなんとかしたい。でもUターン採用もうまくいかない」――そんな悩みを抱える経営者の方こそ、一度M&Aという手法を検討してみる価値があるかもしれません。採用の常識に縛られず、柔軟な発想で会社の未来を切り開く。地方企業のさらなる発展を目指すうえで、M&Aは“採用課題を解決するための一手”となり得るのです。