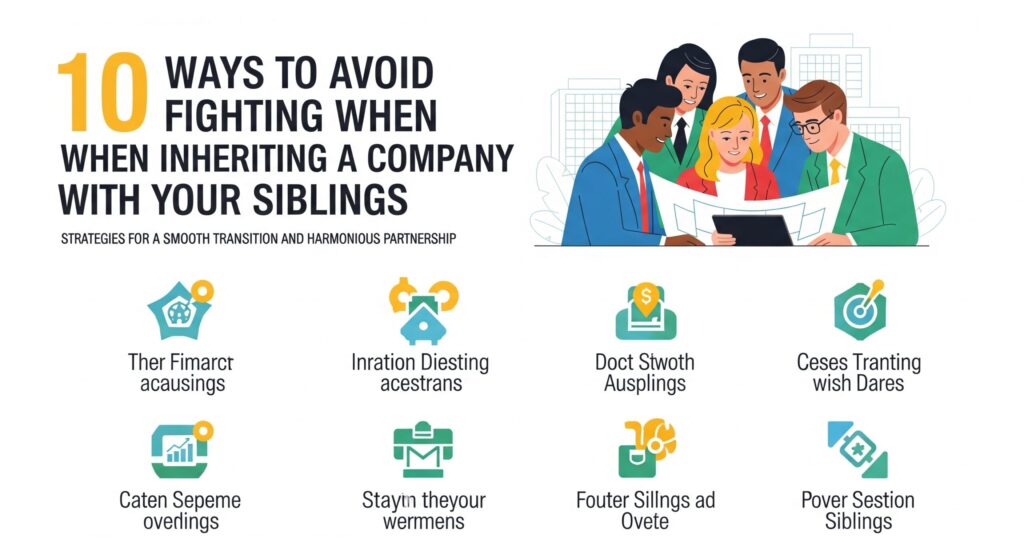「うちは兄弟仲が良いから、相続で揉めることなんてない」
「息子たちに会社を継がせるが、二人で力を合わせてうまくやってくれるだろう」
多くの創業経営者は、このように楽観的に考えがちです。しかし、会社の相続、特に兄弟で事業を引き継ぐケースは、最もトラブルに発展しやすい典型的なパターンの一つです。これまでどんなに仲が良かった兄弟でも、会社という大きな財産と経営権が絡むと、些細なことから亀裂が生じ、修復不可能な「争族」へと発展してしまうことは決して珍しくありません。
「兄弟だから大丈夫」という根拠のない信頼こそが、最も危険な火種です。
この記事では、兄弟での会社相続におけるトラブルを未然に防ぎ、円満な事業承継を実現するための具体的な「10のルール」を、「親(現経営者)がすべきこと」と「兄弟(相続人)がすべきこと」に分けて、徹底的に解説します。
なぜ兄弟での会社相続は、高確率で揉めるのか?
対策を講じる前に、まずは兄弟間の相続がなぜ揉めるのか、その構造的な原因を理解しておく必要があります。
原因1:「平等」と「公平」の勘違いが生む不満
親は子供たちを「平等」に扱いたいと願うものです。しかし、会社の相続において、株式を兄弟で均等に分ける「平等」は、多くの場合、経営の混乱を招き、結果として誰も幸せにならない「不公平」な状況を生み出します。経営を担う兄弟と、そうでない兄弟の貢献度やリスクは全く異なるからです。この「平等」と「公平」の履き違えが、不満の温床となります。
原因2:経営方針の対立と主導権争い
兄弟が共同で経営する場合、お互いの価値観や経営方針が異なると、必ず対立が生まれます。「堅実に行きたい兄」と「積極的に投資したい弟」など、意見が割れた際に最終的な意思決定者がいなければ、経営は停滞し、やがては主導権争いに発展します。対等な立場であればあるほど、この問題は深刻化します。
原因3:それぞれの家族(配偶者など)という「第三のプレーヤー」の登場
兄弟間の問題が複雑化する最大の要因の一つが、それぞれの配偶者やその親族の存在です。「あなたの貢献度に比べて、給料が安すぎるのではないか」「なぜお兄さんの言うことばかり聞かなければいけないのか」といった、家族からの意見が介入することで、兄弟間の小さな不満が増幅され、問題が感情的にこじれていきます。
【親(現経営者)が必ずやるべき5つのこと】揉め事の種を摘み取る準備
円満な兄弟承継の実現は、親である現経営者の生前の準備にかかっていると言っても過言ではありません。未来の紛争の種を、今のうちに一つずつ摘み取っておくことが責務です。
ルール1:後継者の「主」と「従」を明確に指名する
最も重要なルールです。兄弟に会社を継がせる場合でも、必ず「誰が最終的な経営責任者(代表取締役)なのか」を明確に指名してください。そして、もう一方はそれを支える立場であることを、本人たちに明確に伝え、納得させることが不可欠です。「兄弟二人で社長」といった曖昧な形は、必ず将来の対立を招きます。会社の指揮系統は一つであるべきです。
ルール2:「遺言書」で株式の行き先を法的に確定させる
あなたの意思を法的に実現させるために、「遺言書」(公正証書遺言が望ましい)は必須です。遺言書で、経営の主導権を握る後継者に議決権の過半数(できれば3分の2以上)の株式を相続させることを明記しましょう。口約束だけでは何の意味もありません。経営権が安定する株式の配分を、法的に確定させることが、争いを防ぐ最大の防波堤となります。
ルール3:経営に参加しない兄弟への「代償財産」を必ず用意する
もし、経営に参加しない兄弟がいる場合、その相続人が不満を抱かないような配慮が絶対に必要です。後継者に株式を集中させる代わりに、他の兄弟にはそれに相当する別の財産(預貯金、不動産、生命保険金など)を用意しておく「代償分割」の準備をしましょう。これが、後々の遺留分トラブルを防ぐ上で極めて重要になります。
ルール4:兄弟間の「雇用契約」と「報酬ルール」の土台を作る
相続発生後、兄弟がどのような立場で会社に関わり、どのような報酬体系で働くのか、その基本的なルールを生前に親子で話し合い、土台を作っておくべきです。「兄は社長だから月給150万円、弟は専務だから100万円」といった具体的な役職と報酬のルールを決めておくことで、「頑張っているのに報われない」といった感情的な不満を防ぐことができます。
ルール5:専門家を交え、家族会議でオープンに議論する
これらの重要な決定は、決して密室で行うべきではありません。税理士や弁護士など、事業承継に詳しい第三者の専門家を交えて、定期的に家族会議を開きましょう。専門家が中立な立場でファシリテーターを務めることで、感情的な対立を避け、冷静かつ建設的な議論が可能になります。親の想いをオープンに伝える絶好の機会にもなります。
【兄弟(相続人)が必ず守るべき5つのこと】会社と家族を守る協定
親の準備と並行して、相続人である兄弟自身も、将来にわたって良好な関係を維持し、会社を発展させるための「協定」を結ぶ必要があります。
ルール6:相続発生後、速やかに「株主間契約」を締結する
これは兄弟間の「憲法」とも言える重要な契約です。株主間契約では、①株式を第三者に勝手に売却しない、②役員の選任・解任のルール、③意見が対立した場合の解決方法、④一方が会社を辞める場合の株式の買取価格や条件などを、法的な拘束力を持つ書面として定めます。親族間の甘えを排し、ビジネスパートナーとしての関係を明確にするために不可欠です。
ルール7:それぞれの役割と責任範囲を明確に文書化する
「兄は営業と資金繰り、弟は製造と総務」というように、お互いの役割分担(ミッション)と責任範囲を明確にし、文書で共有しましょう。「言った・言わない」の争いを防ぎ、お互いの業務に干渉しすぎることなく、それぞれの分野でプロフェッショナルとして尊重し合う関係を築くための基本です。
ルール8:会社の重要事項に関する「意思決定プロセス」を決める
日常業務は各々の責任者に任せる一方、多額の設備投資や新規事業への参入、人事に関する重要事項など、会社の将来を左右するテーマについては、どのように意思決定を行うのか、そのプロセスを具体的に決めておきましょう。「必ず兄弟で協議する」「一定額以上の投資は双方の合意を必須とする」などのルールが有効です。
ルール9:将来の「出口戦略(株式の売却・退職など)」を事前に話し合う
永遠に兄弟で経営を続けるとは限りません。将来、どちらかが会社を去りたくなった場合や、病気などで経営が困難になった場合にどうするのか、という「出口戦略」を事前に話し合っておくことも重要です。その際の退職金の額や、保有株式の取り扱い(誰がいくらで買い取るのか)を定めておくことで、将来起こりうる紛争を未然に防ぎます。
ルール10:感情的になる前に、中立な第三者(顧問など)に相談する
どんなにルールを決めても、兄弟間ではどうしても感情的な対立が起こり得ます。そんな時は、当事者だけで解決しようとせず、会社の顧問税理士や弁護士など、双方をよく知る信頼できる第三者に相談する仕組みを作りましょう。客観的なアドバイスが、冷静さを取り戻すきっかけになります。
まとめ:円満な兄弟承継は、親の周到な準備と兄弟の固い約束から生まれる
兄弟での会社相続は、決して「性善説」だけで乗り切れるものではありません。それは、血のつながった家族であると同時に、会社の未来を左右するビジネスパートナーになることを意味するからです。
親は、愛情と同時に厳しい現実を見据え、法とルールに基づいた盤石な準備をすること。
そして兄弟は、お互いを尊重し、ビジネスライクな契約を交わすこと。
この両輪が揃って初めて、円満な兄弟承”継”は、骨肉の”争”いを乗り越え、会社をさらなる発展へと導く力強いエンジンとなるのです。
複雑な兄弟間の事業承継は、経験豊富な株式会社勝継屋にご相談ください
「兄弟にどうやって話を切り出せばいいか分からない」
「うちの家族構成に合った、具体的な株式の配分を教えてほしい」
「株主間契約書など、法的な書類の作成をサポートしてほしい」
兄弟間の事業承継は、法律や税金の問題以上に、家族間のデリケートな感情が複雑に絡み合う、非常に難しい問題です。当事者だけで話し合うと、どうしても感情論になり、話がこじれてしまいがちです。
そんな時こそ、私たち株式会社勝継屋のような、事業承継を専門とする第三者の出番です。
私たちは、数多くの兄弟承継の事例を手掛けてきた経験豊富な専門家集団です。中立な第三者の立場から、皆様の家族会議に参加させていただき、円滑な議論の進行をサポートいたします。また、遺言書の作成支援から、もめないための株主間契約の策定まで、法務・税務の両面から、貴社とご家族にとって最適なオーダーメイドの承継プランをご提案し、その実行までを責任をもって伴走いたします。
家族の絆と、大切な会社を守るために。まずはお気軽に、私たちの無料相談をご利用ください。