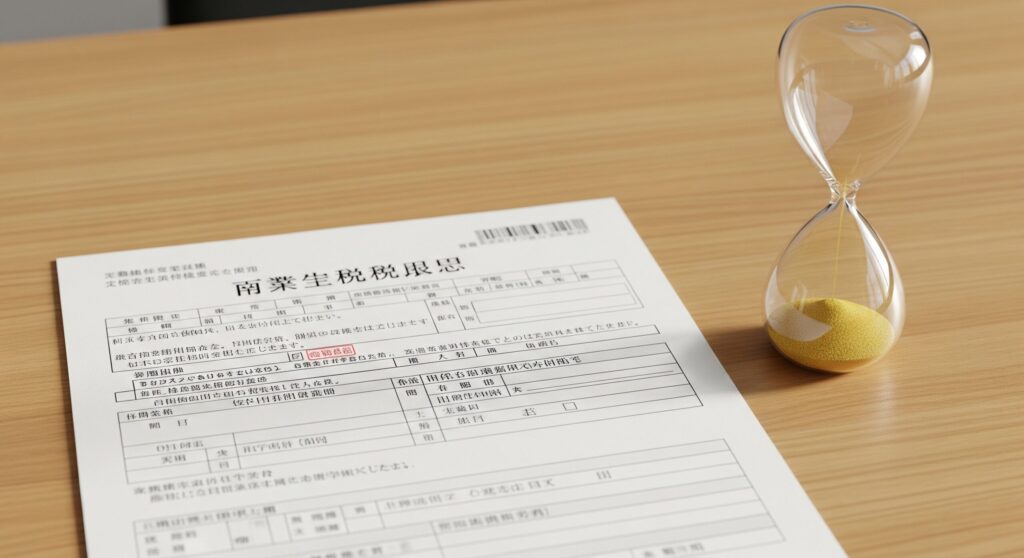「急なことで、生前贈与の準備が間に合わなかった…」
「もしものことがあっても、会社を継がせる時に税金で困らないようにしたい」
中小企業の経営者にとって、会社の未来を左右する「事業承継」。その際に大きな問題となるのが、自社株の引き継ぎにかかる多額の税金です。特に、後継者へ生前贈与する準備が整わないまま相続が発生してしまった場合、「もう事業承継税制は使えないのでは?」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、事業承継税制は、先代経営者が亡くなり、相続が開始した後でも適用を受けることが可能です。この制度は、生前贈与だけでなく、相続による承継も対象としており、適切な手続きを踏むことで、相続後の税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
本記事では、M&Aや事業承継を考える中小企業の経営者やそのご家族に向けて、事業承継税制が相続後でも適用される仕組み、その際の具体的な手続き、そして利用する上での注意点を、どこよりも分かりやすく徹底解説します。大切な会社を未来へつなぐための税金対策として、この知識をぜひインプットしてください。
1. 事業承継税制は「相続」も適用対象!その仕組みを理解しよう
事業承継税制(法人版・特例措置)は、非上場会社の自社株式(議決権のあるもの)を後継者が取得した場合に、その株式にかかる贈与税や相続税の納税を100%猶予し、最終的に免除する制度です。この制度は、以下の2つのケースで適用されます。
- 生前贈与による承継: 現経営者が生きている間に、後継者へ自社株を贈与するケース。
- 相続・遺贈による承継: 現経営者が亡くなり、後継者が自社株を相続または遺贈(遺言によって財産を受け取ること)によって取得するケース。
つまり、相続が発生した後でも、事業承継税制を適用して相続税の納税猶予を受けることは可能なのです。
1-1. なぜ相続後でも適用されるのか?
事業承継税制は、中小企業の円滑な事業承継を支援し、廃業を防ぐことを目的としています。相続はいつ発生するか予測できないことが多いため、生前贈与に限定してしまうと、多くの企業が制度を利用できないことになります。そのため、相続発生後の承継も制度の対象として、柔軟な対応を可能にしているのです。
特に、特例措置では、納税猶予の対象となる株式が100%に拡大され、複数後継者への承継も可能になったことで、相続による承継においてもそのメリットは非常に大きくなっています。
1-2. 相続で適用される「納税猶予」の具体的な内容
相続で事業承継税制を適用する場合、後継者が取得した自社株にかかる相続税の100%が納税猶予されます。そして、その後継者が次の後継者へさらに事業承継した場合や、後継者が死亡した場合には、猶予されていた相続税が免除されることになります。これは、納税義務が事実上なくなることを意味します。
2. 相続後に事業承継税制を適用するための具体的な手続きと期限
相続発生後に事業承継税制を適用する場合、特に「期限」を意識した迅速な対応が求められます。
2-1. 【重要】「特例承継計画」の策定と提出(原則は相続発生前)
事業承継税制の特例措置を利用するためには、原則として、**事前に都道府県知事の確認を受けた「特例承継計画」を提出している必要があります。**この計画書には、会社の事業内容、後継者、承継後の経営計画などが記載されます。
- 原則の提出期限: 令和8年(2026年)3月31日まで
- 相続後に提出する場合の特例: 相続が発生する前に特例承継計画を提出できなかった場合でも、令和8年3月31日までに相続が発生していれば、相続後に計画を作成・提出し、都道府県知事の確認を受けることが可能です。ただし、この場合、相続税の申告期限(相続開始の翌日から10ヶ月以内)までにすべての手続きを完了させる必要があるため、非常にタイトなスケジュールとなります。
2-2. 都道府県知事への「認定申請」
特例承継計画の確認を受けた後、実際に相続が発生したら、改めて都道府県知事へ「認定申請」を行います。
- 申請期限: 相続開始の翌日から8ヶ月以内
- 目的: 会社、先代経営者、後継者がそれぞれ制度の要件を満たしているかを審査してもらい、認定を受けるための手続きです。認定がなければ税務署での猶予申請には進めません。
2-3. 税務署への「相続税申告」と「納税猶予の適用申請」
都道府県知事の認定を受けたら、いよいよ税務署への手続きです。
- 申告期限: 相続開始の翌日から10ヶ月以内
- 内容: 相続税の申告書を作成し、その中で事業承継税制の適用を受ける旨を記載します。都道府県知事の認定書の写しや、その他必要な書類を添付して提出します。
- 担保の提供: 猶予を受ける相続税額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。通常は、相続で取得した自社株式自体を担保とすることで問題ありません。
2-4. 相続時精算課税制度との併用
相続時精算課税制度は、生前贈与で一定額まで贈与税が非課税となり、贈与者の相続時に相続財産に加算して相続税を計算する制度です。
- 事業承継税制との併用: 特例措置では、事業承継税制と相続時精算課税制度を併用することが可能です。これは、万が一、事業承継税制の納税猶予が取り消された場合でも、相続時精算課税制度を適用していれば、贈与税額が抑えられる(あるいは、すでに贈与税を納税済みであれば、その金額が最終的に支払うべき相続税から差し引かれる)など、税務上のリスクを軽減する効果があります。
- 後継者が子や孫でなくても併用可能に: 特例措置の適用を受ける場合には、従来の相続時精算課税制度の要件(60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与)が緩和され、子や孫でない後継者への贈与でも併用が可能になりました。
3. 相続後に事業承継税制を適用する際の留意点とリスク
相続後に事業承継税制を適用することは可能ですが、時間的な制約や手続きの複雑さから、いくつかの留意点やリスクがあります。
3-1. スケジュール管理の徹底が不可欠
相続税の申告期限(10ヶ月以内)というタイトな期間で、特例承継計画の作成・提出、都道府県知事への認定申請、税務署への申告と納税猶予の適用申請、担保提供といった一連の手続きを全て完了させる必要があります。
- 対策: 相続が発生したら、できる限り早く事業承継税制に詳しい税理士などの専門家に相談し、綿密なスケジュールを立てて手続きを進めることが不可欠です。
3-2. 他の相続人との協力が重要
遺産分割協議で自社株式を後継者が取得することに他の相続人の同意が必要な場合があります。また、事業承継税制の適用を受けること自体にも、他の相続人の理解と協力が求められることがあります。
- 対策: 生前中に、事業承継の意向や税制活用のメリットなどを、他の相続人に説明し、理解を得ておくことが理想です。遺言書で後継者に自社株式を承継させる旨を明確にしておくことも、相続時のトラブルを避ける上で有効です。
3-3. 後継者の要件(代表権・役員経験)の確認
相続の時点で、後継者がすでに会社の役員を務めていたか、また相続後に速やかに代表権を取得できるかが重要になります。
- 対策: 先代経営者がご高齢の場合、万が一に備え、後継者候補を早めに役員に就任させ、代表権を譲る準備を進めておくことが望ましいです。相続開始の翌日から5ヶ月以内に後継者が代表者に就任すれば要件を満たすとされますが、余裕を持った準備が不可欠です。
3-4. 継続要件と取消リスクは相続後も続く
納税猶予が開始された後も、後継者が事業を継続し、雇用要件などを満たし続ける必要があります。これらの要件を遵守できない場合、猶予が取り消され、多額の税金と利子税を一括で支払うことになるリスクは、相続後に適用した場合でも同様です。
- 対策: 税制適用後の継続的な報告義務や、経営における制約(M&Aの制限、資産管理会社化の禁止など)を十分に理解し、継続して専門家のサポートを受けましょう。
4. まとめ:相続後の事業承継税制活用も、適切な準備とプロのサポートで
事業承継税制は、先代経営者が存命中に生前贈与の準備が間に合わなかった場合でも、相続による承継でも適用可能な、中小企業にとって非常に心強い制度です。これにより、後継者は高額な相続税の負担を回避し、事業の継続と発展に集中できる大きなメリットを享受できます。
- 相続でも適用可能: 事業承継税制は、相続・遺贈による自社株の承継も対象。
- 期限の意識: 特例承継計画の提出(原則相続前、特例で相続後も可能)、都道府県認定申請(8ヶ月以内)、税務署申告(10ヶ月以内)と、タイトな期限が設けられている。
- 要件確認とリスク理解: 後継者の役員経験・代表権、継続要件、取消リスクなどを深く理解しておく。
- 相続時精算課税制度との併用: 税務リスク軽減のため、併用も検討。
しかし、相続後に適用を受ける場合は、時間的な制約が非常に厳しく、手続きも複雑です。他の相続人との調整や、後継者の要件充足なども重要となります。
そのため、相続が発生したら、できるだけ早く事業承継税制に精通した税理士やM&Aアドバイザーなどの専門家に相談し、綿密な計画とサポート体制のもとで手続きを進めることが何よりも重要です。専門家の知見を最大限に活用し、混乱を最小限に抑えながら、大切な会社を未来へと力強くつなぐことができるでしょう。